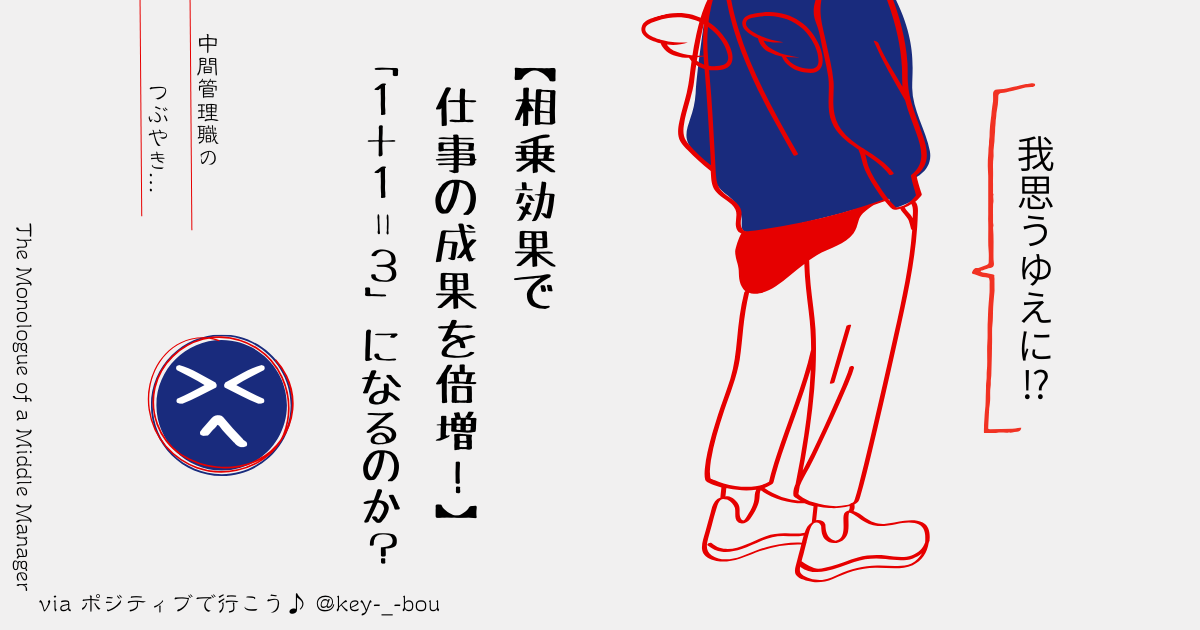
【相乗効果で仕事の成果を倍増】「1+1=3」になるのか?
仕事において、人は「1+1=3」になるのだろうか?
「1+1=3」という表現は、ビジネスや組織において、個々の力が単純に足し算されるだけでなく、互いに協力することで相乗効果が生まれ、より大きな成果を生むという意味を持っているといわれています。
この考え方は「シナジー(相乗効果)」と呼ばれています。
規模の大小いろいろありますが、会社と会社のコラボレーション、M&Aなども含まれますね。
そういった大きなことではなく「中間管理職の場合」にはですよ...。
少ないリソースでなんとか成果をあげていこうってなると...「1+1=3」...なんと魅力的な言葉なことでしょう。
ただ、みなさん、ちょっと待ってくださいね。
「1+1=3」の式ですが、だいたいにおいて大きな見落としがあります。
これ、少なくとも「1=1」であって欲しいのですが、そうでない場合があるのにも関わらず「1+1=2以上」を考える場合が多いんだと思います。
さらには「1以上の人+相性の悪い1以上の人=1以下」といった混ぜるな危険となる場合もあります。
そしてプロジェクトを進めるにあたって、リーダーは1人ですが、メンバーは複数必要になりますので単純な「1+1=○○」とはいかないのです。
とはいえ、シナジー効果が生まれなければ、より大きな成果は生まれにくいと「いわれがち」なのです。

Via George Becker by Pexels
そこで、 まずは「1+1=3」になる場合と、「1+1=2以下」になる場合を見ていきましょう。
「1+1=3」になる場合
相互補完:
メンバーがそれぞれ異なる強みやスキルを持っており、お互いを補完できるときに相乗効果が生まれます。
例えば、1人が技術面に強く、もう1人がコミュニケーションに優れている場合、それぞれの得意分野が活かされ、全体の成果が個々の能力の単純な合計を超える結果を生むことがあります。
協力的な環境:
良好なコミュニケーションや信頼関係があるチームでは、アイデアの共有やフィードバックが活発に行われ、個々の貢献が結集されて大きな成果につながります。
互いに助け合い、支え合うことで、1+1以上の成果が出ることがあります。
創造的な問題解決:
複数の視点やアイデアが集まると、個人では思いつかない革新的な解決策が生まれることがあり、これはしばしばチームの成果を飛躍的に向上させます。
「1+1=2以下」になる場合
重複や対立:
メンバーのスキルや役割が重複していたり、意見が対立して非生産的な議論が続くと、全体の効率が落ちてしまいます。
協力がうまくいかない場合には、個々の貢献が合わさっても期待以上の成果が得られないどころか、むしろ減少することもあります。
コミュニケーション不足:
メンバー間で情報共有が不十分であったり、誤解が生じると、協力の効果が発揮されにくく、個々の力がうまく結びつかないことがあります。
その結果、全体としての成果が期待を下回ることがあります。
リーダーシップの欠如:
適切なリーダーシップがないと、チームの方向性が定まらず、個々の貢献がばらばらになり、結果として1+1が2以下ことどまることがあります。
では、何が3になる為に大事なのか?
「1+1=3」になるためには、チームのメンバーが多様なスキルを持ち(磨き)、良好なコミュニケーションが確立され、信頼関係が築かれる環境が必要です。
一方で、「1+1=2以下」になる場合は、役割の不明確さやコミュニケーション不足、リーダーシップの欠如が主な要因となります。
これらの課題を意識し、解決策を講じることで、シナジーを生み出しやすい環境を整えることが重要だといえそうです。
個々の能力の研鑽、お互いの協力しようという気持、信頼関係、メンバーを引き立てられるリーダーシップ、そしてやはりコミュニケーションの重要さ、必要な機器や道具も大事ですよえね、これらの環境を整えることこそが中間管理職の仕事の1つなのかもしれませんね。
では、 具体的にはどうするべきか...
まぁ、結局、「ケース バイ ケース」なのですよ。
一つとして同じ場合なんてないのだから...似ているケースがあったとしても、それは参考程度にしかなりません。 時期や時代が違う、メンバーも違う、なんなら商品やサービス、問題点がほんの少し違うだけでまったくの別物です。
ただし、ある程度普遍的なことは、勉強、そして実践、さらに分析、でもって改善...repeat...所謂「PDCAサイクル」に、さらに速さ(即応性)が求められているんじゃないでしょうか。
チームとしての目標、リーダーの目標、個人の目標、日々の業務や雑務...「1」って何???
シナジー効果も大事なんだろうが、まずは「1」をどうするかが喫緊の課題でもあるようにも思うんだよなぁ...。
現在、私、上期の査定評価中なのですが...シナジー...シナジー...シナジー......シナジードリンク*1が欲しい...どうやら私、ちょっと疲れているようです。
本日のオススメ1:書籍「プロフェッショナルの条件」
ピーター・ドラッカーやマイケル・ポーターなどの経営学者が、組織や企業におけるシナジー効果の重要性を提唱しました。
特に、企業が他の企業と統合する際によく使われるようになりましたが、心理学やチームダイナミクスの研究においても、協力することで、個々の力を超える成果が得られるという研究がなされています。
基本的には「セルフマネージメント」について学ぶ感じであり、ドラッカーのものの見方や考え方が詰まった本となっております。
ちなみに、私、この本読んだの20年くらい前だと思います。
当時の自分にとって「目からウロコ」だったと思います。 たとえばですが、成果=お金...だけじゃない、成果=人の成長、成長したからお金を生むのです。
まず、成長ありきで、なんで学習するのか?もっといえば何のために生きてるの?頑張っていこうね!?いえ、頑張ろうって思えたように記憶しています。
本日のオススメ2:カクテル「レッドブルウォッカ」
飲み過ぎは良くないのですが、とっておきのエナドリをご紹介しておきます。
「レッドブル」x「スミノフ ウォッカ」の組み合わせ
※お酒は20歳を超えてから、20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。
エナドリの甘味をスッキリとしたウォッカが飲みやすくしてくれています。
とっても元気がでます!
※アルコールが入ってますので、よし!仕事しようとはなりませんけどね。
それでいて、カフェイン効果で眠りにくくなるうえに酔いにくくなる...飲みやすい...永遠に飲めちゃうってわけです。さらに言うと、カフェインもアルコールも依存しやすい傾向にあります。
※月1回程度に抑えておいてください(カフェインxアルコールの摂取は、お互いに過剰摂取になりやすいそうです)
よく、この飲み物の組み合わせはダメとかいわれていますが...そもそも何でも飲みすぎは良くないのです。
異なる2人のシナジー...異なる2種類の飲料によるシナジー...
私、今夜は「いいちこ x 氷 = とっても美味しい いいちこ ロック」を一杯飲んでから寝ようと思います。
そうだ...ついでに、これ、佐久間さんに聞いてみようかなぁ?